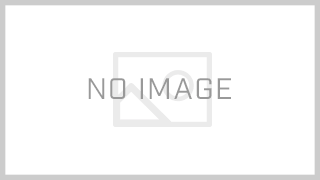サツマイモ栽培で鶏糞肥料を使うかどうか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。サツマイモは痩せた土地でもよく育つ作物として知られていますが、適切な施肥管理によってさらに収量を増やすことができます。特に鶏糞は、窒素やリン酸、カリウムなどの栄養をバランスよく含む有機肥料として注目されています。
一方で、鶏糞の使い方を誤るとツルボケを引き起こし、イモの収量が減少してしまう危険性もあります。この記事では、サツマイモ栽培における鶏糞肥料の特徴や、土壌環境に応じた適切な使用方法、他の有機肥料との組み合わせ方などについて、具体的にご説明していきます。
この記事のポイント!
- 鶏糞肥料に含まれる栄養成分と、サツマイモの生育への効果
- サツマイモ栽培における適切な鶏糞の使用量と施肥時期
- ツルボケを防ぐための鶏糞の正しい使い方
- 土壌環境や栽培目的に応じた効果的な肥料の選び方
サツマイモ栽培で鶏糞肥料を使うメリットと施肥方法
- 鶏糞はサツマイモ栽培に適した肥料である
- 鶏糞に含まれる肥料成分の特徴と効果
- サツマイモ栽培における適切な鶏糞の使用量
- 鶏糞肥料の散布時期と散布方法のポイント
- 鶏糞の過剰施肥によるツルボケの危険性
- 土壌環境に応じた鶏糞の使い分け方
鶏糞はサツマイモ栽培に適した肥料である
鶏糞は、窒素の含有量が他の堆肥と比較して少なく、サツマイモの生育に必要なカリウムが多いことが特徴です。サツマイモ栽培において、窒素量を多く必要としないため、鶏糞は土づくりの堆肥として非常に適しています。
特に、土壌改良の観点から見ると、鶏糞は土壌の物理性(排水性・通気性)を改善する効果があります。サツマイモは水はけの良い土壌を好むため、この点でも鶏糞は理想的な選択肢となります。
鶏糞の肥効に関して興味深い特徴があります。窒素成分は約1ヶ月でほとんど効果が切れますが、リンやカリは継続的に植物に吸収されていきます。この特性は、サツマイモの生育サイクルと相性が良いと言えます。
一般的な畑では15㎡あたり105kgもの鶏糞堆肥を使用した例もあり、大量施用による収量増加の効果も確認されています。ただし、これは特殊な事例であり、通常の栽培では土壌状態に応じて適量を判断する必要があります。
サツマイモ栽培では、肥沃過ぎない土壌のほうが良質なイモが収穫できます。鶏糞の使用は、この点を考慮しながら行うことが重要です。
鶏糞に含まれる肥料成分の特徴と効果

鶏糞に含まれる窒素は約2%と少なめで、15kgの鶏糞に含まれる窒素は約300gです。リンとカリを加えても1kgにも満たず、残りの14kgは腐葉土のような有機質として働きます。
鶏糞の窒素成分は、投入後約1ヶ月でほぼ無機化され、その後はあまり効果が出ません。これはバクテリアによって分解されやすい形となっているためです。一方で、リンやカリは土中に残り、植物が継続的に吸収できる状態となります。
サツマイモは10アール当たりの養分吸収量として、窒素9.6kg、リン酸6.3kg、カリウム28.2kgを必要とします。鶏糞はカリウムを多く含むため、この養分要求に適しています。
サツマイモは窒素固定細菌との共生によって空気中から窒素を固定できるため、肥料からの窒素供給は少なくて済みます。鶏糞の低窒素・高カリウムという特徴は、この点でもサツマイモ栽培に適しています。
肥料の効果を最大限に引き出すには、土壌のpHを5.5~6.0に調整することが重要です。鶏糞の施用と併せて、必要に応じて土壌のpH調整を行うことをお勧めします。
サツマイモ栽培における適切な鶏糞の使用量
基本的な使用量として、1平方メートルあたり500g~1kgの鶏糞を施用することが推奨されます。これは一般的な家庭菜園での目安となる量です。
特に水はけの悪い土地では、20~30cmの高畝栽培を行い、その際に鶏糞を混ぜ込むことで効果的です。野菜の生育が良好な肥えた土壌の場合は、鶏糞の量を控えめにすることが賢明です。
堆肥や鶏糞は生育を遅らせ、水っぽいイモになりやすい特徴があるため、使いすぎには注意が必要です。肥料は植える前に入れる元肥として使用し、追肥は行わないようにします。
前作で他の野菜を栽培していた畑では、土壌中に肥料分が残っている可能性があります。このような場合は、鶏糞の使用量を更に減らすか、場合によっては無施肥で栽培することも検討できます。
実際の使用量は土壌状態によって大きく異なるため、まずは少なめの量から始めて、生育状況を見ながら調整していくことをお勧めします。
鶏糞肥料の散布時期と散布方法のポイント
鶏糞の散布は植え付けの2~3週間前に行うのが最適です。この時期に散布することで、土壌と鶏糞が馴染み、植え付け時に適度な状態となります。
散布方法としては、まず圃場全体に均一に鶏糞を撒き、その後よく耕うんして土と混ぜ合わせます。耕うんの際は、20~30cm程度の深さまでしっかりと耕すことが重要です。
畝立ての際には、さらに土とよく混ざるように注意を払います。水はけを考慮して、畝の高さは20~30cm程度確保し、畝幅は50cm、株間は30~35cm程度を目安に設定します。
マルチを使用する場合は、鶏糞を混ぜた後にマルチを張ります。マルチングにより地温が安定し、肥料の効きも安定することが期待できます。
植え付け後の追肥は避けるべきです。追肥を行うとツルボケの原因となり、イモの収量に悪影響を及ぼす可能性があります。
鶏糞の過剰施肥によるツルボケの危険性
ツルボケとは、肥料、特に窒素成分が効きすぎることで起こる現象です。茎葉が過剰に成長する一方で、イモの肥大が抑制されてしまいます。
鶏糞を過剰に施用すると、一時的に窒素が多く供給され、ツルボケを引き起こす可能性があります。特に肥沃な土地では、少量の施用でもツルボケのリスクがあるため注意が必要です。
ツルボケの症状が出た場合、カリウムを多く施肥することである程度抑制できますが、完全な解消は困難です。そのため、予防が最も重要となります。
肥料過多の兆候として、茎葉の異常な生長や濃い緑色の葉の出現などがあります。これらの症状が見られた場合は、次回の栽培では鶏糞の使用量を減らす必要があります。
鶏糞の効果は土壌に残るため、次作以降も考慮した施肥計画を立てることが重要です。同じ場所でサツマイモを栽培する場合、2年目以降は無肥料栽培も検討できます。
土壌環境に応じた鶏糞の使い分け方
痩せた土地や砂地の場合、鶏糞の施用は土壌改良と栄養補給の両面で効果を発揮します。この場合、標準的な使用量を目安に施用を行います。
水はけの悪い粘土質の土壌では、鶏糞と共に有機物を混ぜ込むことで、土壌の物理性を改善できます。この場合、高畝にして排水性を確保することも重要です。
既に肥沃な土地での栽培では、鶏糞の使用は最小限に抑えるか、場合によっては使用を見送ることも検討します。特に前作で葉物野菜を栽培していた場合は、残存している養分を考慮する必要があります。
土壌診断の結果に基づいて施用量を決定するのが理想的です。pHが7に近い場合は、イモの味や色が悪くなる可能性があるため、酸性よりの土壌を維持することを心がけましょう。
サツマイモの生育に適した土作りのためには、鶏糞の特性を理解し、各圃場の状況に応じて適切に使い分けることが成功への鍵となります。
サツマイモ栽培で使う肥料の選び方と鶏糞の活用法
- 堆肥の種類と特徴を理解して選ぶ
- 鶏糞と他の有機肥料の組み合わせ方
- 米ぬかや草木灰との相性と使用方法
- 肥料の残効を考慮した施肥計画
- 土壌診断に基づく鶏糞の使用判断
- まとめ:サツマイモ栽培における鶏糞肥料の上手な活用法
堆肥の種類と特徴を理解して選ぶ
サツマイモ栽培に使用できる堆肥には、牛糞、豚糞、鶏糞、馬糞などさまざまな種類があります。中でも牛糞は、窒素成分が少なくカリウムが多く含まれているため、サツマイモ栽培に適しています。
鶏糞は、窒素2%程度、リンやカリウムも含まれており、15kgの鶏糞のうち実際の肥料成分は1kg未満です。残りの14kgは腐葉土のような有機質として土壌改良に役立ちます。
一般的な堆肥の使用量は、1平方メートルあたり500g~1kg程度が目安となります。ただし、野菜栽培後の肥沃な土壌では、堆肥の使用を控えめにする必要があります。
堆肥や鶏糞は生育を遅らせ、水っぽいイモになりやすい特徴があるため、過剰な施用は避けるべきです。肥料は植え付け前の元肥として使用し、追肥は行わないことが重要です。
サツマイモは涼しくてやや痩せた、乾いた土地で美味しく育ちます。暑くて肥沃な土地や、湿った土地では良質なイモを作るのが難しいため、堆肥の選択と使用量には注意が必要です。
鶏糞と他の有機肥料の組み合わせ方
鶏糞と他の有機質肥料を組み合わせる場合、サツマイモに必要な養分バランスを考慮する必要があります。サツマイモは10アール当たり、窒素9.6kg、リン酸6.3kg、カリウム28.2kgを必要とします。
有機質肥料の組み合わせでは、窒素の供給を抑えながら、カリウムを十分に確保することが重要です。実際に、サツマイモは窒素固定細菌との共生により、空気中の窒素を利用することができます。
土壌改良の観点からは、鶏糞と完熟堆肥を組み合わせることで、土壌の物理性(排水性・通気性)を改善できます。これはサツマイモが好む水はけの良い土壌環境の整備に効果的です。
施肥のタイミングは、植え付けの2~3週間前に行うことが推奨されます。この時期に有機質肥料を施用することで、土壌と肥料が十分に馴染み、適度な状態となります。
サツマイモ専用の肥料を使用する場合は、一般的な肥料と比べて窒素が少なめ、カリウムが多めに配合されているものを選びましょう。これにより、つるボケを防ぎながらイモの肥大を促進することができます。
米ぬかや草木灰との相性と使用方法
米ぬかは、窒素:リン酸:カリウムの比率が2:4:1となっており、サツマイモ栽培に適した有機質肥料の一つです。米ぬかと木灰を組み合わせることで、効果的な施肥が可能となります。
木灰にはカリウムが7~8%含まれており、さらにミネラル成分も豊富です。1平方メートルあたり50g~100g程度の草木灰を施用することで、サツマイモの生育に必要な養分を補うことができます。
施肥の際は、一握り(約30g)の草木灰を目安に散布します。米ぬかと木灰だけでサツマイモ栽培を行っている生産者もおり、シンプルな肥培管理で十分な収量を得られることが確認されています。
サツマイモ専用の化成肥料を使用する場合は、窒素、リン酸、カリウムの割合が1:1.5:2に近いものを選択すると良いでしょう。これは米ぬかと木灰を組み合わせた場合の養分バランスに近い比率となっています。
土壌環境によっては、米ぬかや草木灰の単独使用でも十分な効果が得られる場合があります。特に前作で葉菜類を栽培していた場合は、残存養分も考慮して施肥量を調整する必要があります。
肥料の残効を考慮した施肥計画

サツマイモ栽培では、前作の栽培履歴や残存する養分を考慮した施肥計画が重要です。特に窒素施用量が多い葉菜類を栽培した後は、残存窒素量が多いため、施肥を控えめにする必要があります。
鶏糞の窒素成分は約1ヶ月で無機化されますが、リンやカリウムは土壌中に残り続けます。このため、連作する場合は2年目以降の施肥量を減らすことが賢明です。
サツマイモは連作障害が起きにくい作物ですが、長期の連作ではセンチュウ類の集積などが懸念されます。4年以上に1回程度の輪作や、必要に応じた土壌消毒を検討する必要があります。
肥料の残効は、その土壌の状態や栽培方法によって大きく異なります。例えば、15㎡の圃場に105kgもの鶏糞を施用した事例では、翌年は無施肥でも十分な収量が得られる可能性があります。
サツマイモの品質向上には、土壌のpHも重要な要素となります。pHが7に近づくとイモの味や色が悪くなるため、5.5~6.0の範囲を維持できるよう、施肥計画に含める必要があります。
土壌診断に基づく鶏糞の使用判断
サツマイモ栽培において、土壌診断は適切な施肥量を決定する重要な指標となります。土壌のpHや養分状態を把握することで、鶏糞の必要性や使用量を判断できます。
水はけの悪い粘土質土壌では、20~30cmの高畝栽培が推奨されます。このような場合、鶏糞は土壌改良材としての役割も果たすため、標準的な使用量を目安に施用を検討できます。
肥沃な土壌での栽培では、むしろ肥料を控えめにすることで、より質の良いイモを収穫できる可能性があります。このような場合、鶏糞の使用は最小限に抑えるか、使用を見送ることも検討します。
土壌診断では、特にpH値に注目する必要があります。サツマイモ栽培に適したpHは5.5~6.0の範囲で、これを超えると品質低下の原因となる可能性があります。
品質の良いイモを収穫するためには、土壌の物理性改善も重要です。鶏糞の施用は、通気性や排水性の改善にも寄与するため、土壌の状態に応じた使用を検討します。
まとめ:サツマイモ栽培における鶏糞肥料の上手な活用法
最後に記事のポイントをまとめます。
- 鶏糞は窒素2%程度で、カリウム成分が豊富なサツマイモに適した有機質肥料である
- 標準的な使用量は1平方メートルあたり500g~1kgが目安となる
- 植え付け2~3週間前に施用し、追肥は行わない
- 窒素成分は約1ヶ月で無機化されるが、リンとカリは継続的に効果を発揮する
- 過剰施用はツルボケの原因となるため、土壌状態に応じた適量施用が重要
- 水はけの悪い土壌では20~30cmの高畝栽培が効果的
- 土壌pHは5.5~6.0の範囲に維持することが品質向上につながる
- 前作の残存養分を考慮し、必要に応じて施肥量を調整する
- 米ぬかや草木灰との組み合わせで、より効果的な栽培が可能
- 連作の場合は4年に1回程度の輪作を検討する
- 土壌診断に基づいた施肥設計が、収量と品質の向上につながる
- 肥沃な土壌では、施肥量を控えめにするか無施肥栽培も検討する
当サイトでは、インターネット上に散らばるさまざまな情報を収集し、AIを活用しながら要約・編集を行い、独自の切り口で見解を交えながらわかりやすい形でお届けしています。
情報の整理・編集にあたっては、読者やオリジナル記事の筆者へご迷惑をおかけしないよう、細心の注意を払って運営しておりますが、万が一、掲載内容に問題がある場合や修正・削除のご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
迅速に対応をさせていただきます。
その際には、該当記事の URLやタイトルをあわせてお知らせいただけますと、より速やかに対応 することができますのでそちらもご協力いただけますと大変幸いでございます。
今後とも当サイトをよろしくお願いいたします。